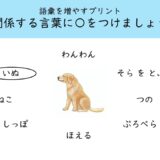もくじ
言語聴覚士が教える!集中力が続かない子どもにも届く絵本の読み聞かせ7つのコツ
「うちの子、すぐ絵本に飽きちゃって…」と感じていませんか?
絵本を読み始めたのに、すぐ立ち上がる。ページをめくる前に別のことを始めてしまう――そんな「集中が続かない子」に、どうやって絵本を読み聞かせたらいいのか、多くの保護者や保育士さんが悩むテーマです。
でも実は、ちょっとした工夫で、絵本がぐっと子どもに届きやすくなるんです。
この記事では普段私が実践している、「集中が弱い子にも効く読み聞かせの7つのコツ」を紹介します。
1. 短くてテンポのよい絵本を選ぶ
集中が続かない子に長編絵本は逆効果。まずは1〜2分で読める短い絵本を選びましょう。
ストーリーがシンプルで、繰り返しが多くリズム感のある作品は特におすすめです。
例:「じゃあじゃあびりびり」「だるまさんが」「いいおかお」など
2. 感情を込めてテンポよく読む
抑揚のない読み方は、子どもにとって「ただの音」になってしまいます。
キャラクターの声を変えたり、驚く場面でちょっと声を大きくするだけで、ぐっと引き込まれます。
少しオーバーなくらいがちょうどいい、と思って読んでみましょう。
3. 子どもに参加してもらう
読み手だけが話す「一方通行」の読み聞かせより、子どもも一緒に参加できる形にするのが効果的。
- 「次、何が出てくると思う?」
- 「この動物、なんて鳴くかな?」
- 「いっしょに“おしまい”って言おう」
こんな呼びかけが、集中力を自然に引き出します。
ページをお子さんにめくってもらうのもおすすめです!
4. “探し遊び”を取り入れる
絵本の中に小さなミッションを仕込むのも効果的です。
- 「このページに赤いりんご、見つけられるかな?」
- 「さっきのネズミさん、どこに行ったかな?」
視覚を使った“探し要素”があると、楽しみながらページを見続けられます。
例:「きんぎょが にげた」「にょっきりんどこどこ」など
5. 途中で終わってもOKにする
「最後まで読まないとダメ」と思い込む必要はありません。
集中力が切れたら、途中でやめても大丈夫です。
「ちょっとだけ読んだけど楽しかったね」と感じる体験の方がずっと大切。
無理に読ませるより、“また読みたい”と思わせる方が次につながります。
6. 導入でワクワクをつくる
読み始める前に、ちょっとした前振り(導入トーク)を入れてみましょう。
- 「この絵本、ちょっと変わったカエルが出てくるんだって」
- 「おばけの絵本だけど、ぜんぜん怖くないんだって!」
「絵本っておもしろい!」と感じてもらうきっかけになります。
7. 絵本の高さを子どもの目線に合わせる
読み聞かせのとき、絵本の位置にも気をつけてみてください。
絵本が高すぎたり角度が合っていないと、子どもにとってとても見づらく、集中が切れやすくなります。
床に座って読むときは、絵本を子どもの目線と同じくらいの高さ・角度に合わせてあげましょう。
視線が安定することで、気持ちも落ち着き、集中しやすくなります。
最後に
読み聞かせは“学び”ではなく、“遊び”に近いもの。
子どもにとって絵本は、大人と一緒に楽しむコミュニケーションツールです。
子どもが集中できなくても、それは「だめなこと」ではありません。
楽しめれば100点!
今日紹介したコツを、ぜひひとつでも試してみてくださいね。